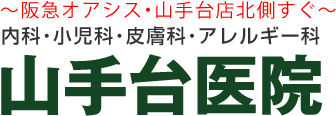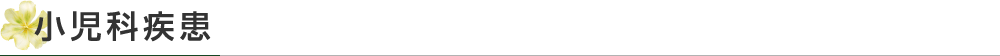発熱、咳(喘息を含む)、鼻水、発疹、嘔気、嘔吐、下痢、便秘、腹痛、アレルギー(花粉症、食べ物、その他)等の症状を呈する小児疾患はいろいろあります。当医院では、それらに対し迅速検査等を通じて、鑑別診断を行い適切な治療薬を選択し加療をしています。
- 解熱剤の使用について
- ウイルスによる感染症の場合、高熱でも元気があれば、服薬せずに様子を見ましょう。発熱する事で原因となるウイルスと戦いウイルスを不活化させています。その時はむやみに、熱を下げる必要はありません。元気がなくしんどそうにしている場合は、38.5度以上で解熱剤(アンヒバ座薬、カロナールの粉末、錠剤、シロップ剤等)を使って下さい。6~8時間あけて、1日に2~3回の使用は可能です。尚、発熱時には白湯、スポーツドリンクなどをこまめに取って、脱水症にならない様にして下さい。熱は朝に下がって夕方に上がってくることが多いです。
- 40度前後の原因不明の高熱
- 中耳炎、川崎病が疑われますので要注意です。また、せき症状が少ないにもかかわらず4日以上の40度前後の発熱は肺炎も疑われます。
- 咳の対策
- ウイルス性かぜによる咳が多いですが、気管支喘息(アレルギー科疾患のところで詳述)、気管支炎(長引く咳には抗生剤を投与)、細気管支炎、クループ、肺炎、マイコプラズマ肺炎、百日咳等には、それぞれ、特徴的な咳を呈していますので早めに受診し適切な治療を受けて下さい。咳こんで嘔吐しそのまま寝込んでしまい、のどが詰まる事も有りますので注意が必要です。
シロップ剤、ドライシロップ剤(水に溶ける粉末剤)、錠剤、テープ剤(ホクナリン、ツロブテロール)等、症状、要望に応じて処方していますのでお気軽に相談してして下さい。
- クループ症候群
- ケンケンという犬の鳴き声に似た乾いたせきをする喉(咽喉頭、声帯)の炎症。顔色の悪化やチアノーゼ呼吸困難がある場合は迷わず救急病院を受診してください。
- 鼻水の4つの原因
- 鼻水の役割は、外の空気を肺に送り込む前の温度調節機能であります。
- 「気温の変化」:寒い日又、冷えた空気を吸った時、鼻の粘膜が刺激され鼻水がでます。朝や夜にひどくなる事が多いです。
- 「アレルギー反応」:さらさらした透明な鼻水、鼻づまり、くしゃみが特徴です。花粉症が原因となることが多いです。
- 「風邪等のウイルス」:風邪が進行してくるとドロッとした黄色~緑色の鼻水がでてきます。細菌感染がある時は抗生剤の内服が必要です。
- 「自律神経の乱れ」:ストレスによる交感神経、副交感神経の乱れにより、緊張状態では鼻水がネバネバになり逆にリラックスしているとサラサラの鼻水がでます。それぞれの鼻水の症状に応じて抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬(オノン、キプレス、シングレア、プランルカスト、モンテルカスト等)、即効性の抗アレルギー薬など又、鼻炎用の噴霧スプレー剤(アラミスト、ナゾネックス、フルナーゼ等)も処方しています。
- おねしょ・夜尿症
- おねしょはありふれた子供の症状です。治療の原則は「起こさず、怒らず、焦らず、ほめる、比べない」事です。原因は抗利尿ホルモンの夜間分泌不足により夜間の利尿が多い事です。抗利尿剤のミニリンメルトのお薬を使用した場合、1年後に約50%が治癒できる様になります。治療のタイミングは遅くとも宿泊行事の3ヶ月前に医院を受診するのが良いでしょう。おねしょ対策の他のお薬(小建中湯、他)も処方しています。
- アナフィラキシー(食べ物及び2回目のハチ刺し後の即時型アレルギー反応等)
- 症状で最も多いのは、蕁麻疹、赤み、かゆみ等の「皮膚症状」。次にくしゃみ、せき、ぜいぜい、息苦しさ等の「呼吸器症状」と、目のかゆみ、唇の腫れ等の「粘膜症状」が多いです。そして腹痛や嘔吐等の「消化器症状」、更には、血圧低下等「循環器症状」もみられます。急激な血圧低下で意識を失う等の「ショック症状」も10%程みられ注意が必要です。蜂に1回刺された人、食物アレルギーのある人はIgE抗体価検査を勧めます。個人で使用できる簡単な簡易注射処置剤エピペン処方もしています。
エピペンを使用すべき症状(以下の症状が一つでもあれば使用すべきです)
~消化器症状~①繰り返し吐き続ける②がまんができない持続する強いお腹の痛み。
~呼吸器症状~①のどや胸が締め付けられる②持続する強い咳き込み③声がかすれる④ゼーゼーする呼吸⑤犬が吠える様な咳⑥息がしにくい。
~全身の症状~①唇や爪が青白い②意識がもうろうとしている③脈を触れにくい、不規則④ぐったりしている⑤尿や便を漏らす。
エピペンの作用:
1)急激な血圧低下に対して血圧を上昇させる。
2)粘膜の腫れ(浮腫)を改善する。
3)息苦しさ等の呼吸苦に対して気管を拡張させる。
4)アナフィラキシー症状を引き起こす体内からの化学物質の放出を抑制する事
等です。
- 腹痛
- 子供の腹痛で最も多いのは「便秘」です。自律神経の発達未熟で夜間に体調が変化し易い為、腹痛が夜間に多くなります。嘔吐を伴う事も有ります。院内で浣腸等の処置を実施しています。他に感染性胃腸炎、虫垂炎、腸重積(ジャム様の血便)が原因となります。
- 赤ちゃんの便秘(約1歳未満)
- ほとんどの赤ちゃんは3日に一回以上の便が出ます。4日以上出ないと、おなかがはったり、ぐずったりする子が多いと思われる為、1歳以上の子と同じ様に、1週間で便の回数が3回より少ない場合に便秘症と考えられます。
治療は、赤ちゃんがウンウンうなっていきむ、かといって出るウンチは硬くない状態は食欲、機嫌が悪くなければ、離乳食開始後に軽快するので治療の必要はありません。気になる方は3日を目安に肛門に人肌程度の湯をスポイドでぴゅっぴゅっとかけて刺激してみてください。それでもだめなら綿棒の先にワセリンを塗り、肛門から1~2cm入れて肛門を広げるイメージでゆっくり、優しく「の」の字を4~5回描くとウンチが出易くなります(綿棒浣腸)。肛門を痛めない様に優しくやれば毎日やる事も可能です。それでも出ない時は以下の説明を参照して下さい。
- 便秘(乳幼児~学童)
- 週に3回より少なかったり、5日以上でない日が続き便を出すのに苦痛を感じれば便秘といいます。小さいコロコロの便や、軟らかい便が少しづつ一日に何回も出ている場合は、腸に便が溜まりすぎて、もれでる様になっているのでこれも便秘です。
便秘になる理由は、①乳児期の母乳からミルク移行期、又は離乳食開始期②幼児期の強制的なトイレトレーニング③学童期の通学開始や、学校での排便ガマン体験等です。それらがきっかけとなり、便が硬くなり、硬い便をだして肛門が切れ、痛い思いをすると、2~3歳のお子さんは、次の排便を我慢してしまったり、肛門の筋肉を締めながら力むようになります。便はしばらく我慢していると、そのまま大腸に便が残ります。大腸は便から水分を吸収するのが仕事ですので、便は益々硬くなり、便がいよいよ出る時に便が更に硬くなってる為、非常な痛みを伴う事になります。お子さんは益々排便を我慢するようになり、悪循環となります。そのような事が続いていると、腸がだんだん鈍感になり排便感覚がなくなり、便秘となっていきます。
便秘が1~2ヶ月以上続いている場合には、「慢性便秘症」と診断され、きちんとした治療が必要となります。
便秘のお薬(下剤)
①便を軟らかくする薬:酸化マグネシウム(カマグ)モニラック、マルツエキス(特に乳児)等。
②腸の動きをよくする薬:ラキソベロン液、テレミンソフト座薬、浣腸等(当院内で処置も可)。
③作用が穏かな漢方薬:小建中湯、大建中湯等。
便秘が慢性化している場合は一度出たからといって安心せず最低2週間は毎日出すように調整します。その後薬を減量していきますが、多くは数ヶ月~年単位の治療が必要です。
- 熱性けいれん(ひきつけ)
熱が出始めてから24時間以内におこる事が多く、突然、体を硬直し、その後手足を震わせて、眼球は上方を向いて白目となり、意識はなくなり、呼吸が荒く不規則になる症状の事です。けいれんはほとんどの場合5分以内に収まり、その後、何事もなくすやすやと眠った状態になります。又、意識がはっきりしなかったり、数分間、一点を見続ける状態も熱性けいれんの一症状です。又、2~3日熱が続いてからけいれんがおこった場合には、熱性けいれんと関係のない髄膜炎や脳炎の恐れがあるので要注意です。突発性発疹の発熱時に初めての熱性けいれんを起こす場合もあります。
熱性けいれんの発症率は約10%で、好発年齢は1~2歳ですが、80%が3歳未満です。(6ヶ月~6歳位までおこります)約30%の子供は再発しますがほとんどの子供は1回だけの発症で終わります。初めてけいれんがおこったらびっくりしてどうしてよいかわからないのが普通です。ほとんどの場合、けいれんは5分以内に止まりますので次の様に処置して下さい。(1)衣服をゆるめて(特に首のまわり)顔を横に向けてください。吐いている様なら嘔吐物で、のどがつまらない様に口や、鼻のまわりを拭いてあげましょう。
(2)歯を食いしばっている時でも、口の中に物を入れないで下さい。吐き気がおこるので何も飲ませないで下さい。薬や飲み物を与えないでください。
(3)今後の治療の参考となりますのでけいれんの形やけいれん持続時間、体温等を記録して下さい。初めてのけいれん発作の時は発作が収まっても救急車を呼ぶ事が多いですがやむを得ないと思います。
次の様な症状があるときは、早めの受診をして下さい。(1)けいれんが長く10分以上続く時か、同じ日に2回以上けいれんがおこった場合。
(2)体の一部分だけが強くけいれんしている時、又、けいれんに左右差が強い時。
(3)けいれんの後に意識が回復しなかったりまひ等、体の動きが悪い時。初回の発作、一才未満の発作の時は受診した方がよいでしょう。けいれんが止まり、その後すやすやと眠っている時は、ダイアップ座薬(当医院で処方できます)があればこれを使ったほうが良いでしょう。 ダイアップを使い熱性けいれんの再発予防をする目安は、
(1)15分以上のけいれんをおこした事がある。
(2)半日で2回以上、半年で3回以上けいれんをおこした事がある。
(3)体の一部で普通とは違う強いけいれんを2回以上おこした事がある。以上の事があり、37.5度以上(38.5度ではない)あれば、ダイアップを1個使い、血中有効濃度を維持する為、8時間後にまだ熱が下がらない時はもう1個使います。座薬をいやがる場合は他の形態の抗けいれん薬もありますので御相談下さい。
ダイアップ座薬を入れてから30分以上たってからアンヒバ座薬(解熱剤)を使って下さい。同時に使うとダイアップがアンヒバの基剤に溶ける為に吸収が悪くなって効果が上がらなくなる恐れがあります。効果発現までの時間はダイアップは15~30分でアンヒバは30分位です。内服の解熱剤なら同時に使っても良いでしょう。熱性けいれんで後遺症が残る事はほとんどありませんので、落ち着いて対応しましょう。
- 夏に気をつける子供の感染症(5月~9月)
プール熱(咽頭結膜熱)、ヘルパンギーナ、手足口病、溶連菌感染症(のどの症状は12月~3月、皮膚の症状は7月~9月に多い)です。共通する症状は発熱、喉と口中の痛みです。それぞれ違った特徴を持っていますので、区別はできます。
院内で迅速検査もできます。プール熱はプールで他人に感染させ易いので検査を受ける方が良いでしょう。のどが痛くて水分が飲みにくくなるので脱水症に注意しましょう。
10分位毎に飲水をうながして下さい。溶連菌感染症は抗生物質で3日位でのどの痛みは取れますが、他の感染症はウイルス性なので抗生物質はありませんが、7日位で自然に治癒する傾向があります。のどの痛みには、痛み止めを処方します。
詳細はそれぞれの疾患説明の所を参照して下さい。
発熱と発疹がある疾患
- ◆溶連菌感染症 発熱、扁頭炎(原因菌は溶連菌以外にインフルエンザ菌、ブドウ球菌、肺炎球菌等で、同様の扁頭炎の症状を呈します)、強い咽頭痛、イチゴの様な舌。手足、体、全身に赤みがかかった点状の少しかゆみのある小発疹が出る事が特徴です。咳や鼻水、下痢等の風邪症状はないことが多いです。当医院では、咽頭ぬぐい液での10分程度の迅速検査で診断しています。(10日~2週間のアモキシリン等の抗生物質の服薬で治療します。治癒後、まれに急性腎炎を発症する事もありますので治癒後2W~1ヵ月後に尿検査をしています。)細菌性感染なので、再感染や家族に感染する事もあります。(潜伏期間:2日~5日)
- ◆風疹(3日はしか) 発熱と同時に全身にやわらかい桃紅色の小発疹と耳後部のリンパ節の腫れが見られます。熱は2~3日で下がります。(潜伏期間:14日~23日)
- ◆水ぼうそう(水痘症) 発熱と伴に体幹、頭髪部等に紅斑(赤み)がでて、数日おいて小さく平らで赤く痛みのある盛り上がった発疹が現れ、その後赤い皮膚の上に水泡ができ、膿胞、最後はかさぶたになる順に皮疹ができていきます。発熱は2~3日で下がりますが、発疹は数日から2週間続きます。空気感染するので伝染し易く、注意が必要です。将来、帯状疱疹を発症する事も稀に有ります。抗ウイルス薬のゾビラックス、バルトレックス等の処方、発疹水泡には、特別な軟膏を使って処置をします。(潜伏期間:10日~21日)
- ◆麻疹(はしか) 高熱と咳、鼻水等のかぜ症状で始まり、流涙、目やにがでる結膜炎、耳の後部から全身に発赤とはっきりした発疹が出て、口の中に白斑が出る事が特徴です。感染力は大へん強いです。2~3日後、一旦、解熱した後再度、発熱した時に発疹が見られる事が多いです。(潜伏期間:7日~18日)
- ◆ヘルパンギーナ エンテロウイルス・コクサッキーウイルスが原因です。4~10月、主に夏に発症する事が多い夏かぜの一種。突然の39~40度の発熱、口腔内の上顎の粘膜、咽頭、扁桃に、小さな水泡、発疹ができます。手足口病と異なり手や足に発疹は見られません。多くは咽頭痛があるので、つばを飲み込む事が困難になり、よだれが多くなったり嘔吐しやすくなったりする事があります。熱は2~3日後位に下がりますが、咽頭痛は残ります。(潜伏期間:3日~6日)
- ◆川崎病(MCLS、好発年齢は4才以下ですが、多くは一才未満の乳児の原因不明の高熱疾患) ~六つの主要症状~
①最初は頚部リンパ節の腫れ(首が腫れるが小さい子でははっきりしない)②5日間以上続く40度前後高熱(これは第一条件)③次に手のひらや、足の裏が赤くなり硬く浮腫状に腫れた様になります。④様々なパターンの全身の発疹。⑤目やにの出ない結膜の充血(目が赤くなる)が見られますがはっきりしない事もあります。⑥口唇が赤くなり、唇がひび割れて出血したり、又、舌が赤くブツブツになるイチゴ舌もみられる事もあります。BCG接種部位の発赤が重要な診断の助けになる事も有ります。(約3%の人に心臓の冠動脈の拡大や瘤「こぶ」ができる後遺症が残る事もあります。)入院してガンマグロブリン注射等で治療します。 - ◆ヘルペス性発疹 発熱後、唇、舌に水泡、発疹が見られます。抗ウイルス性の内服薬、軟膏の処方をしています。
- ◆かぜ症状があるウイルス性発疹 原因ウイルスは200種類以上あります。発疹はかぜをひいて2~3日後に出ます。特に夏かぜに多く2~3日後に自然に消えます。
- ◆伝染性単核球症 咽頭痛、嚥下痛、イチゴの様な舌、首のリンパ節やまぶたの腫れ、発疹、肝脾腫等。
- ◆突発性発疹 1歳前後の発疹(発熱なし)で詳述(潜伏期間:10日)
発熱はあるが(発疹はない)疾患
- ◆マイコプラズマ肺炎 初期症状は風邪と同じですが鼻症状(くしゃみ、鼻水)は少なく、37度~38度の発熱がみられ、咳が目立たず、頭痛、気分不快、倦怠感等のよくある風邪症状が数日続きます。その後、乾いた「コンコン」という痰の出ない、いつもと違う激しいカラ咳が続きます。熱が下がった後もしばらくつらい状態が続きます。治療しないと熱が下がっても咳は3~4週間続きます。当医院では、咽頭ぬぐい液での15分位の迅速検査で診断を実施しています。従来の抗生物質に耐性があり効果のない薬もありますので慎重に抗生物質を選んで処方しています。(潜伏期間:1週間~4週間)
- ◆おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) 耳下腺・顎下腺の腫れと痛みが特徴です。高熱を出す事も有りますが2~3日で下がります。一般的に片側からはじまり、1~2日間で両側が腫れてきます。片側しか腫れない場合もあります。腫れは1週間~10日間でおさまります。(ワクチンを接種した人は症状が軽い場合もあります。抗体価を検査する事で、免疫の有無を調べられます。)合併症に副睾丸炎、難聴、無菌性髄膜炎等が有ります。痛みに対して鎮痛剤等の処方をしています。(潜伏期間:12日~25日)
- ◆百日咳 かぜ症状の後、息を吸う時にヒューという音が出る特有の咳の発作を繰り返します。マクロライド系の抗生物質が良く効きます。(潜伏期間:5日~12日)
- ◆プール熱(咽頭結膜熱) 多くはプールで流行、伝染します。急に高熱(39度~40度)が5日前後続きますが、加えて特徴的なのが、結膜炎です。眼が充血したり、痛みを伴い、目やにや涙が出ます。眼の症状は一般的には片方から始まりますが多くの場合はもう一方にも広がります。又、強いのどの痛みがある咽頭炎、膿がついている扁頭炎の発症が特徴です。眼の症状がない場合も有ります。頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛等も見られる事も有ります。解熱した後、咳が出る事も有ります。食欲がなくなる事も多いですが、水分は飲めて熱の割りに比較的元気な事も有ります。原因はアデノウイルスで当医院では、咽頭ぬぐい液による15分位の迅速検査で診断します。(潜伏期間:2日~14日)
- ◆インフルエンザ 初めに突然高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身倦怠感(しんどい)の症状が出ます。他、鼻水、咳、咽頭痛の症状が出たり、又、腹痛、下痢、嘔吐も時に出る事が有ります。タミフルカプセル又は、タミフルの粉末剤、イナビル、リレンザ等の吸入剤、ラピアクタ点滴剤で治療します。薬剤師が常勤していますので、薬はすぐに手渡しできる態勢を取っています。尚、迅速検査で陽性反応が出ない場合でも、臨床症状で判断し抗ウイルス剤等を処方しています。(潜伏期間:1日~4日)
- ◆RSウイルス感染症 冬に流行し、乳児の半数以上が1歳までに、ほぼ100%が2歳までに感染し、その後も一生、再感染を繰り返します。4~6日の潜伏期の後、水の様な鼻汁、ひどい、むせる様な乾いた咳、発熱(38.5度以上の発熱は少ない)等の症状が現れます。多くの場合1~2週間で治癒します。約3割の子供は気管支炎や細気管支炎を発症し、「呼吸が浅くなる、ゼイゼイする、痰がつまる、呼吸数が増える多呼吸(1分間に60回)、呼吸をさぼる無呼吸」等の症状が現れてきます。1~3%の子供が入院治療を受けます。ワクチンはありません。15分程度の迅速診断キッドで診断しますが、年齢によって保険が効かない事があります。(潜伏期間:2日~8日)
- ◆日本脳炎 頭痛、嘔吐、けいれん、意識障害、昏睡等。
- ◆細菌性下痢症(食中毒) 全身倦怠感、寒気、ふるえ、嘔吐、下痢、腹痛、しぶり腹、膿粘血便等の症状が特徴です。鶏肉、豚肉、魚介類の生食、半生食、他、細菌が付着した包丁やまな板上での調理が原因となります。原因菌は、キャンピロバクタ(下痢便の色がオレンジがかっている。鶏肉、卵、牛レバーに注意)、病原性大腸菌O157、サルモネラ菌(下痢便の色が緑っぽい。卵、肉、うなぎに注意)、黄色ブドウ球菌(手指でさわったおにぎり、サンドイッチに注意)、腸炎ビブリオ(魚介類に注意)等です。マクロライド系抗生剤、ホスミシン等の抗生剤で治療します。3~4日の経過で改善します。(潜伏期間:1日~8日)
-
◆ウイルス性感染性胃腸炎
・ノロウイルス腸炎 強い嘔気、頻回の嘔吐下痢が特徴です。淡黄色の下痢便の事が多いです。下痢便、嘔吐物を処理する家族への伝染(空気感染)が見られますので注意が必要です。生牡蠣、ホタテ貝が感染原因といわれています。11月~3月の冬に流行します。(潜伏期間:12時間~48時間) ・ロタウイルス腸炎 生後6ヶ月~2歳が好発年齢で、1月を中心に5度以下になる冬が感染のピークです。激しい水溶性下痢便と頻回の嘔吐が特徴で白色~灰白色~薄茶色の下痢便の事が多いです。便を処理する時に乾燥浮遊した便汁中、又、嘔吐物のウイルスで大人に空気感染し、重症になる事も有りますので注意が必要です。(潜伏期間:1日~3日) ・アデノウイルス腸炎 通年、主に夏に多いです。下痢が多く嘔吐は少ないです。腹痛、微熱、のどの痛みを伴います。3歳未満の乳児に多いです。 - ◆結核症 2週間以上続く咳、痰、発熱、元気がない、疲れやすい、寝汗等。(潜伏期間:2年以内)
発疹が見られる疾患(発熱なし)
- 1歳前後までの発疹(発熱なし)
-
- ◆アトピー性皮膚炎 体、手足の屈曲部、首の後ろ、耳の後ろの赤みとかゆみ。(皮膚科アレルギー疾患で詳述)
- ◆乳児脂漏性皮膚炎 (1~4ヶ月)頭、額のかさぶた、白色ロウ状の皮膚。
- ◆乳児湿疹 (1~4ヶ月)顔、胸のカサカサ、ジクジク状の皮膚。保湿剤、軟膏の処方。
- ◆突発性発疹 (6ヶ月~2歳)39~40度の高熱が出る事が多いです。生後初めての発熱後、3~4日後に熱が突然平熱まで下がると共に風疹様の小発疹が顔や体に出た後、3日間で消える事が特徴です。下痢、咳、まぶたのむくみを伴う事もあります。高熱の割には比較的元気な事が多いです。熱性けいれんを起こす割合も多いです。(潜伏期間:10日)
- ◆カンジダ性皮膚炎(カビによる皮膚炎) 下痢の後におしり、肛門周囲の皮膚が真っ赤になるのが特徴です。(ステロイド軟膏を塗ると悪化します。抗カンジダクリームを処方します。)ただし、おしりのしわのところが赤くなければ、かびが原因ではない、おむつ皮膚炎なのでのでステロイド軟膏で治ゆしますがまったく異なる薬なので、正確な診断を受けましょう。
- 1歳からの発疹(発熱なし)
-
- ◆じんましん 全身、時に、限局的に、発疹、みみず腫れ(膨隆した)様発疹が見られ、発赤、かゆみがあります。(アレルギー疾患で詳説)
- ◆単純ヘルペス性感染症 発熱はないが、指、顔、他の部位に発疹、水泡が見られます。抗ウイルス薬の内服、軟膏等の処方をします。(潜伏期間:2日~14日)
- 3、4歳からの発疹(発熱なし)
-
- ◆手足口病 エンテロウイルス・コクサッキーウイルスが原因です。発熱しない事が多いですが37~38度位に発熱することもあります。発疹は縁(ふち)が赤くて真ん中が白い米粒大のやや硬めの水泡が特徴です。手足には指の筋に沿った細長い水泡ができます。てのひらや足裏にも水泡がでますが、時々、腕、脚、膝、臀部に出る事も有ります。口の中にも水泡ができる事もあります。少し痛がゆい事も有りますが普通は無症状です。1週間位で治癒します。見た目は派手ですが、ヘルパンギーナより元気な場合が多いです。口の中の水泡が原因でよだれ、食欲低下もみられます。(潜伏期間:3日~6日)
- ◆リンゴ病(伝染性紅斑) 発熱はなく、発疹の数日前に軽い鼻水倦怠感の症状が有りますが、気がつかない事が多いです。まず、両頬にリンゴ様の紅斑(赤み)、その後、特に上腕、又、上肢、大腿(太もも)、脚、胴体の順にレース状、網目状・地図状等の発疹の拡散が見られます。ヒトパルボウイルスによる感染症なので、大人に伝染すると関節痛、筋肉痛等の症状がでます。(潜伏期間:4日~21日)
- ◆その他 とびひ、水イボ、草木かぶれ、毛虫かぶれ等があります(皮膚科疾患で詳述)。